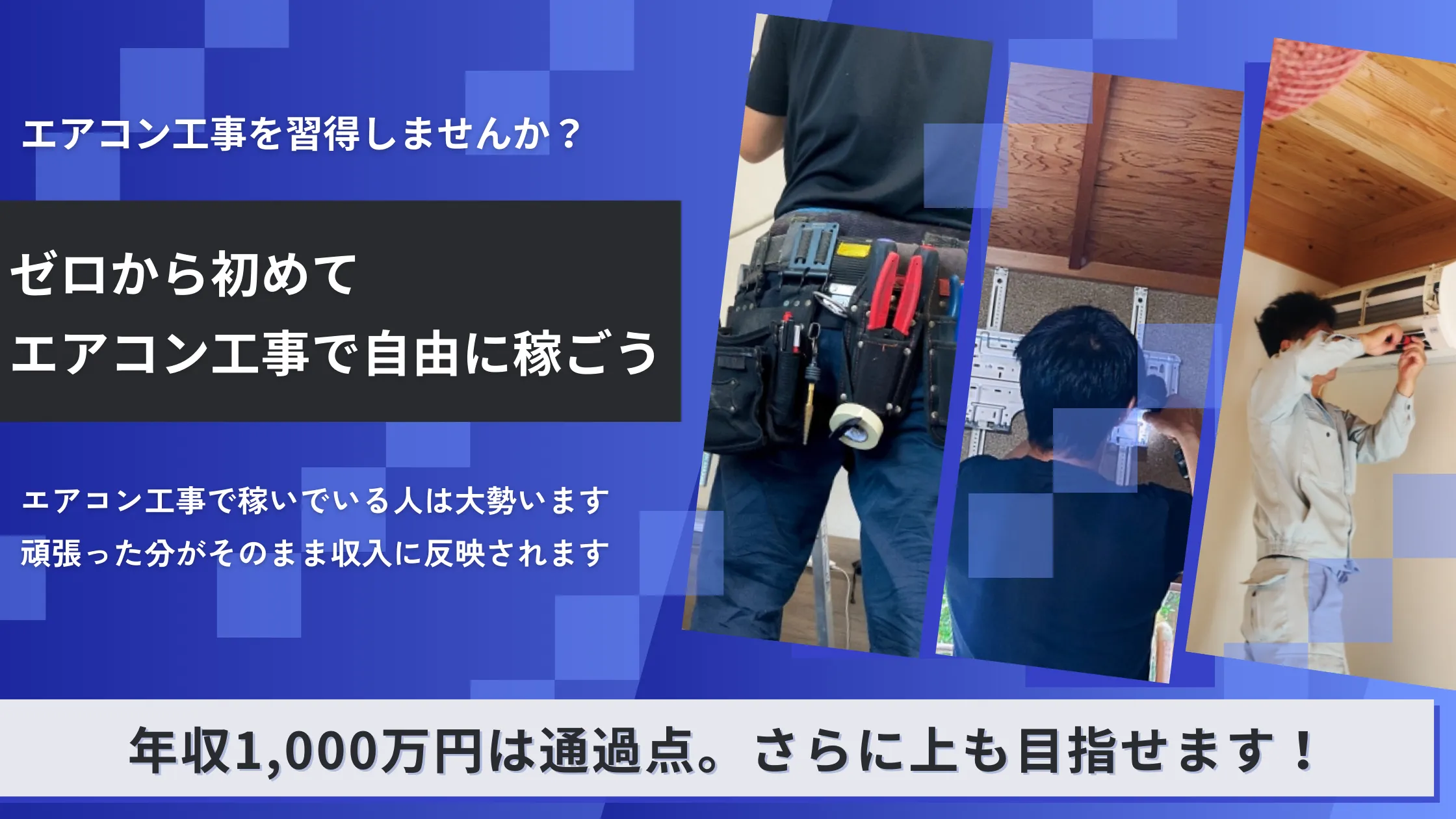現場で起きたトラブル事例と対処法
はじめに
エアコン工事は、見えない壁の裏、配管の中、屋外機の設置環境など「隠れた条件」が味方にも敵にもなる仕事だ。どれだけ事前準備をしていても、「これは想定外だったな…」というトラブルは必ず起きる。だが、トラブルをどう対応したかで、信頼度が決まる。この記事では、我々が過去に直面したリアルなトラブル事例を交えながら、その対処法と予防策を詳しく伝える。読む人には「この会社は現場をもっとも理解してるな」「この会社と協業すれば安心だな」と感じてもらえるように。
トラブル事例①:配管ガス漏れ発覚
起きた状況
ある現場で、完了検査を終えて引き渡し直前、「室内のスリットから冷房の風が弱い」という連絡を受けた。調査してみると、室外機付近の配管接続部に微細なガス漏れが起きていた。
原因分析
- フレア加工が不十分でシール性が甘くなっていた
- 締め付けトルクが規定値に達していなかった
- 接続部にごみ混入や金属カスが挟まって、配管同士の密着が悪くなった
これらは典型的な「施工精度」の問題。
対処法
まず、冷媒ガスを回収して真空引きをやり直す。漏れ箇所を界面活性剤水溶液で塗って泡付き検査をし、漏れを可視化。問題箇所を再フレア加工、接続部のパッキング再調整、そして再度トルクレンチで指定トルクで締め付け。最終的に真空引き後24時間以上圧力保持テストをして異常がないことを確認して引き渡した。
予防策
現場では、フレア作業後に「バックナットを先締め → 本ナットを仮締め → 最終トルク締め」という手順を必ず踏む。接続前にゴミ・切粉混入がないかルート洗浄をする。締め付けトルク管理表を持っておき、締め忘れ防止チェックを行うプロセスをチームで徹底する。
トラブル事例②:水漏れ(ドレン排水不良)
起きた状況
梅雨時、運転を始めたら室内機から水滴が垂れてきたという連絡。現場に急行したところ、ドレンホースの傾斜が逆勾配になっており、排水がスムーズに流れていなかった。
原因分析
- ドレンホースを通す際に曲げがきつすぎて水が流れにくくなった
- ドレンホース途中に高い位置で折れ曲がりやくぼみができていた
- ドレンパン内にホコリやスラッジ(汚泥)が堆積して、排水孔を塞いでいた
対処法
まず室内機を少し取り外してドレンパンやホース内部を清掃。高圧エアーでホースを抜けるように流す。ドレンホースをできるだけ緩やかな勾配(最低でも1/100〜1/200程度)をつけて配管し直し。途中固定具で曲がりを防止。さらにドレンアップポンプなどを設置すべき現場では併用して対処。試運転で水が問題なく流れるか確認して完了。
予防策
設置前に排水ルートをシミュレーションして傾斜を確保。ホコリ・砂が混入しやすい建築段階なら配管中に異物が入らないよう保護キャップをつける。設置後に試運転時にしばらく散水して、排水能力を確認。定期メンテナンス時にもドレンチェックをするルーチンを組む。
トラブル事例③:室外機設置場所トラブル/近隣クレーム
起きた状況
ある戸建てで、屋根上設置を依頼された室外機を設置したところ、6か月後に隣家から騒音クレームが来た。調査すると、室外機の振動が隣家壁に共振して音が伝わっていた。
原因分析
- 室外機の防振が甘く、振動が構造体に伝わっていた
- 室外機の設置面が不均一で、強度不足の金具がたわんでいた
- 屋根板材の膜振動を誘発する形状・共振モードがあった
対処法
室外機を一旦取り外し、防振ゴムの性能を見直した(高減衰タイプを採用)。設置金具を強固な鋼材に替え、取り付け面の剛性を確保。振動吸収マットを敷設し、壁側との距離を確保。隣家に対して防振対策を説明・謝罪し、音の低下を確認後に再稼働。同時に周波数帯・音圧レベルを測定し、基準値以内を確かめた。
予防策
事前に周囲の建物との距離や壁との干渉、振動伝達経路を想定。設置金具は余裕を持った耐荷重設計にする。振動吸収材やマウント材の選定を現場条件に合わせて行う。設置後に簡易音響チェックをして、不安要素を早期に潰す。
トラブル事例④:壁穴破損・建材損傷
起きた状況
新築物件で、貫通穴を開ける際に筋交いにビスを打ってしまい、壁材が割れてしまった。お客様からクレームがあり、補修費用の請求を求められた。
原因分析
- 図面確認・墨出しを十分にしていなかった
- 隠れた構造材を無確認で穴あけした
- 電動ドリル先端のブレや位置ズレでずれてしまった
対処法
まず現場停止してお客様に謝罪。被害部分を撮影・記録し、補修業者と協力して修復案を提出。必要なら専門補修屋と連携して補修・美装を実施。工事保証責任として補修費用を自社負担。以降、墨出しと穴あけ位置のダブルチェック体制を強化。
予防策
図面と現地を重ね合わせて隠れ構造体(筋交い、配管、間柱など)の位置を事前把握。レーザー墨出し機や探査器(レーダー、金属探知機等)で下地を確認。穴あけは事前に小径ドリルで小穴を開けて確認後、本穴拡大のステップを踏む。
トラブル事例⑤:追加費用トラブル/認識齟齬
起きた状況
お客様から「工事日当日に “追加で◯万円かかる” と言われた。そんな話は聞いてなかった」とクレームを受けた。見てみると、配管距離が基本範囲を超えていたり、壁貫通穴、電源工事などが追加工事扱いになっていたケース。
原因分析
- 見積もり時に基本工事範囲(配管長さ、穴あけ、電源設置など)を明確に説明していなかった
- お客様との仕様確認書面化が不十分で、口頭理解で進めていた
- 現場条件変化(下地構造、隠蔽配管、予期せぬ電気配線干渉など)に柔軟な対応が契約に反映されていなかった
対処法
まずお客様と現場で追加工事項目を一つひとつ確認し、理由を丁寧に説明。可能なら金額交渉して一部負担を当社で引き受け、信頼関係を維持。次回以降に使う「仕様チェックシート」や「条件付見積もり条項」を新たに提供。お客様からの了承サインを取って工事着手。
予防策
見積もり段階で「標準範囲」と「追加対象」を明示した仕様書を出す。配管長、穴あけ位置、電源状況、隠蔽構造、特殊設置などの想定を漏れなく聞き取る。お客様と現場下見を実施し、写真付きで条件共有。見積もり同意後、工事着手前に「最終確認チェックリスト」で仕様すり合わせを行う。
まとめ:信頼を守る“トラブル対応力”こそ強み
トラブル事例を並べただけでは読者の心は動かない。「その現場でどう動いたか」「どうお客様に説明したか」「どこまで責任を取ったか」が肝。だからこそ、上記の事例と対処法、予防策を自社ブログに載せる時は、可能な限り現場写真、図解、ビフォーアフター、工事担当者のコメントを交えて読む人にリアルを伝えよう。
協力業者様の成長は、私たちの成長の源。
そして私たちの成長は、協力会社さまの成長につながる、そんなウィン・ウィンの共存共栄の関係こそが、事業運営を営む中で最も重要視すべきことだと考えています。
自社の成長を加速させるためにも、協力業者様を全力で支援することをお約束いたします。
株式会社APJを支えてくれる協力業者様に深く感謝を込め、業務を通じて協力業者の皆さまの人生が豊かになるお手伝いをしたい。
エアコン工事協力業者様からのご応募をお待ちしております。
All People Joy ― 全ての人に喜びを。
TEL:0120-870-807
MAIL:info@n-apj.co.jp
 株式会社
株式会社